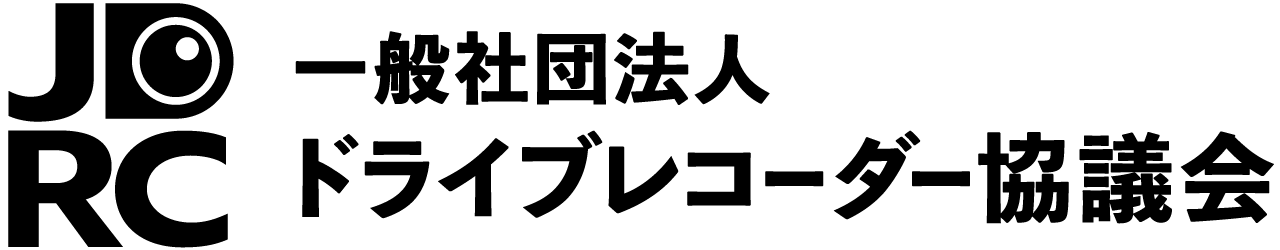個人会員
名誉会員一覧(五十音順・2024年6月現在)
- 浮穴 浩二
- 小林 敏雄
- 堀野 定雄
- 吉本 堅一
- 龍 重法
個人会員一覧(五十音順・2024年11月現在)
- 青木 宏文(名古屋大学)
- 阿賀 正己(東京農工大学)
- 阿部 友保(株式会社 東海DC)
- 石川 博敏(認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク)
- 今長 久(一般財団法人日本自動車研究所)
- 北村 憲康(東京海上ディーアール株式会社)
- 久保 登(東京大学)
- 島崎 敢(名古屋大学)
- 立石 圭太(エファード株式会社)
- 永井 正夫(東京農工大学・日本自動車研究所)
- 丹羽 洋典(合同会社 nitro・にわ法律事務所)
- ポンサトーン ラクシンチャラーンサク(東京農工大学)
- 道辻 洋平(茨城大学)
- 宮嵜 拓郎(認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク)
- 山田 一郎(東京大学)
- 山本 幸裕(テクノコ株式会社)
- 渡部 大志(埼玉工業大学)